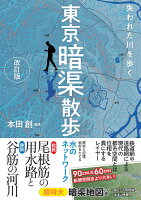先日訪れた清水窪湧水で湧水に興味を持ちました。
この時、なんというか、「水が湧き出ている」という場所を他でも見てみたい。そう思ったんですね。
さっそく身近な場所で探して見ると、渋谷の「鍋島松濤公園に湧水の池」がある、ということがわかりました。
現在の渋谷に湧水の池があるというのは驚きです。
事務所が渋谷なので、仕事帰りに散歩してみることにしました。
<目次>
- 鍋島松濤公園のあるところ。
- 鍋島松濤公園の歴史。
- 湧水の池は、遊具のある広場を過ぎた奥にあります。
- 鍋島松濤公園の湧水の池。
- 水が湧く場所は見えず。しかし豊富な水量があるのがわかります。
- 池の周りを歩く。
- 公園の入口は北側と東側にもあります。
- 建築家、隈研吾さんデザインのトイレ。
- 鍋島松濤公園の湧水は渋谷駅方向へ。暗渠の上の遊歩道。
- 撮影に持っていったカメラ。
- 【追記】カルガモの親子が撮影できました。
鍋島松濤公園のあるところ。
鍋島松濤公園(なべしましようとうこうえん)
〒150-0046 東京都渋谷区松濤2−10−7
京王井の頭線神泉駅より徒歩約5分。渋谷駅からは約15分です。
常時開放されていて、入園料は無料。

渋谷駅から松濤文化村ストリートを歩き、途中Y字の別れ道を過ぎればすぐに到着します。
簡単な道順なので、Googleマップ等で確認しておけば迷うこともないでしょう。
渋谷はかつて沢山の川が集まる谷だったので、水が湧き出ている場所があっても不思議ではないのですが、大都会である渋谷駅から続く繁華街の先、ということを考えると、やっぱり驚きます。
鍋島松濤公園の歴史。

案内板を要約します。
- 江戸時代は紀州徳川家の下屋敷と、旗本長谷川家の屋敷があった場所です。
- 明治5年(1872年)になって、旧佐賀藩主鍋島家がその跡地を購入し茶園を開きました。その名が「松濤園」で、ここから町名がついたそうです。
- 「松濤」とは茶の湯のたぎる音から出た名で、この銘のお茶を生産していました。
- 大正13年(1924年)鍋島家が児童公園として施設をつくって公開。
- 昭和7年(1932年)東京市に寄付されました。
- 昭和9年(1934年)から渋谷区に移管、戦後に渋谷区立の公園になったそうです。
明治の頃は、渋谷に茶畑があったのには驚きです。湧き水で淹れたお茶はきっと美味しかったでしょう。明治末期には渋谷のお茶は衰退してしまったそうで、とても残念ですね。
湧水の池は、遊具のある広場を過ぎた奥にあります。

公園の敷地に入ると、子供たちの声が響いています。
遊具も複数設置されており、保護者の方を含めなかなかの賑わいをみせていました。
緑が豊で、遊具も充実している公園です。
鍋島松濤公園の湧水の池。

ISO400 , 1/160s , f/8
遊具のある広場を抜け、池側にきました。
広場と違って、こちらは人も疎ら。
水車のある静かな池が見えてきました。
「静謐な」とまではいきませんが、谷戸に湧いた水でできた池で、周りを緑に囲まれた雰囲気のある場所です。
水が湧く場所は見えず。しかし豊富な水量があるのがわかります。

鍋島松濤公園の湧水はかいぼりを行ったとき、池底に9地点で湧き出しているのが確認されたそうでうす。
(前回のかいぼりは2014〜2015年にかけておこなったそうです。)
また、調査では1時間あたり約1000ℓの湧水が湧き出しているのが、水量の増加から計測されています。
つまり、湧水の水量は1日約24トン、かなりの水が湧き出ていることになります。
かいぼりの後は、水も綺麗になりカワセミもいたようです。
(しばらく池の周りにいましたが、カワセミの姿は確認できませんでした。)

池の周りを歩く。

ISO400 , 1/40s , f/8
程よい間隔でベンチが置かれています。
おやつがわりなのか、おにぎりを食べたりしている人もいました。
お昼は、こちらでお弁当を食べるのもいいと思います。

ISO400 , 1/320s , f/8
水辺の水車やたくさんの樹木が、渋谷の原風景を感じさせます。
この日、水は流れていましたが、水車は回ってはいませんでした。

ISO400 , 1/100s , f/8
池の小島には松の木もあります。
小島の手前には水生植物のアサザが見えます。
小さな葉が浮かんでいます。
花は初夏から秋に咲くそうです。数は少ないですが見ることができました。

ISO400 , 1/320s , f/5.6
秋なので花は少し。
ツワブキです。他の花が少ない時期に咲き、丈夫で日陰でも育ちます。
キク科の植物だからか、原風景的なイメージがします。
日本庭園などでも、よく見かけますね。

ISO400 , 1/160s , f/8

ISO400 , 1/100 , f/8
夕日の入り方が綺麗です。
木の葉を抜けてくる光に目を奪われます。

ISO400 , 1/200s , f/4
鳩もいました。
一周するのに5分もかからない、一目で見渡せる広さの小さな池です。
ちょっとした気分転換に、ぶらりと寄ってみるのもいいと思います。
公園の入口は北側と東側にもあります。


ISO400 , 1/125s , f/8
出入り口は高い場所にあり、池が窪地にあるのがわかります。
といっても、それほど高低差があるわけではないので、景色の変化にちょうどいいくらいです。

ISO400 , 1/2000s , f/5.6
途中で見つけた灯籠。
昔からの灯籠なのか、柵に囲われていました。
建築家、隈研吾さんデザインのトイレ。

杉板のルーバーがランダムに垂直方向に取り付けられています。
風景に馴染んでいるような、いないような。。。
正直、違和感もありますが個人的には好感が持てるデザインです。

案内板はあるのですが、ぱっと見、どこに入ればいいのかわかりませんでした。
実際には、使う方と使用目的に応じて内装や備品が違うというものです。
5つの個室があり、ベビーチェア、ベビーベットが備え付けられていたり、車椅子や着替え用に広だったりします。
「掃除が大変そう」と思ってしまいました。
このトイレは、日本財団が行う「THE TOKYO TOILET(ザ トウキョウ トイレット)の一つ。誰でも快適に利用できる公共トイレを設置するプロジェクト。代々木深町小公園の「透明なトイレ」(建築家、板茂さんデザイン)が話題を呼びました。
鍋島松濤公園の湧水は渋谷駅方向へ。暗渠の上の遊歩道。

ISO400 , 1/800s , f/8
鍋島松濤公園の湧水はどこへいくのでしょう。
松濤文化村ストリートと並走する路地が、レンガ舗装の暗渠となっています。
こちらの暗渠は松濤支流と呼ばれるそうで、神泉谷支流と鍋島松濤公園からの水の流れが合流したものだそうです。
神泉谷支流は、「弘法湯」が利用した井戸、「神泉館」にあった池など、かつて神泉駅周辺にあった水源の水を流している暗渠になります。
この暗渠は東急百貨店本店の敷地、文化村のコンサートホールにぶつかって終わりとなります。
渋谷には暗渠が多いと思いましたが、渋谷だけでなく、東京全体に暗渠は沢山あります。
参考にしている本はこちら。
こちらの本も参考にしています。
その源流を辿れば、今尚、水が湧く場所が残っているようです。
湧水があるところ、続く暗渠と散歩してみたいですね。
撮影に持っていったカメラ。

持っていったのは、コンパクトなソニーのα7RⅢ。レンズはSonnar T* FE 35mm F2.8 ZA(SEL35F28Z)というコンパクトなセットです。
ここからの写真は全てこのセットで撮影しています。
写真はトリミングなし。RAWデータからキャプチャーワンで現像。画像調整をしています。
撮影データを書きましたが、明るさなども調整してしまっているので、目安くらいに思っていただければ幸いです。
カメラはSONY α7RⅢ。
新型はマイナーチェンジして背面モニターが良くなっているそうです。
レンズはSonnar T* FE 35mm F2.8 ZA(SEL35F28Z)。
コンパクトで使いやすい焦点距離35mmのレンズです。発売が2013年とちょっと古いレンズになってきましたが、今でも十分に綺麗な描写です。
レンズフードはサードパーティ製のものに変えてあります。
【追記】カルガモの親子が撮影できました。
渋谷の繁華街に隣接するこの公園で、カルガモのヒナが孵化し育っていました。本当にちっちゃくて可愛いですよ。